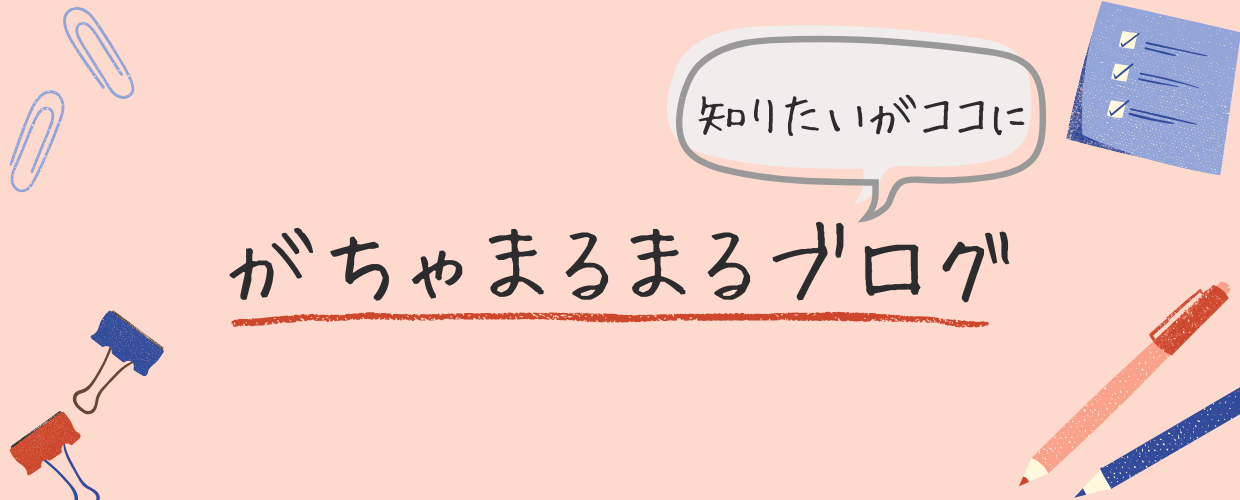「通勤手当=非課税」はもう昔の話かもしれません。
実は通勤手当にはすでに一定の税金がかかっており、2025年以降はさらに増税の可能性も指摘されています。

これまで会社から支給される通勤手当を「そのまま手元に入るお金」と考えていた人にとっては、大きな影響があるかもしれません。
特に電車やバスの定期代が高騰する中で手取り額が減る事態になれば、毎日の生活にも影響が出るでしょう。
この記事では
- 通勤手当はどのような課税をされているのか
- 2025年以降に何が変わる可能性
についてお伝えします。
通勤手当はすでに課税されてる?

通勤手当は所得税の面では非課税ですが、社会保険料の計算には含まれており、その分だけ手取り額が減る仕組みになっています。
つまり、私たちは知らず知らずのうちに“サイレント課税”されているのです。
どうやって課税されているのか?

まず、通勤手当の課税について整理しておきましょう。
基本的に、通勤手当は以下の2つの側面から考える必要があります。
所得税の非課税枠
通勤手当には、一定額まで所得税がかからない「非課税枠」が設けられています。
例えば、公共交通機関を利用する場合、
です。
しかし、これを超える部分については課税対象となります。
社会保険料の計算対象
所得税がかからなくても、社会保険料(厚生年金や健康保険)の計算には通勤手当が含まれます。
つまり給与と同じように社会保険料の算定基準となる「標準報酬月額」に反映されるため、実質的には負担増となっています。
この点について多くの人が
と疑問を抱いています。
SNSでも「通勤手当が実費ベースなら社会保険の算定に入れないのが筋では?」という声があり、不公平感が指摘されています。
通勤手当はどんな人がもらえるの?

そもそも通勤手当とは、会社が従業員に対して支給する「通勤にかかる費用の補助金」です。
これは、公共交通機関の運賃や自家用車通勤にかかる費用(ガソリン代や駐車場代)などを補填する目的で支給されるものです。
通勤手当は、基本的に以下のような条件を満たす従業員に支給されます。
しかしながら、すべての従業員が必ずもらえるわけではありません。
たとえば、以下のようなケースでは支給されないこともありますよ。
通勤手当の支給条件や金額は企業ごとに異なるため、就業規則を確認することが重要です。
通勤手当|2025年以降さらに増税でマイナスとは?

本来なら自分の持ち出し分が発生するのはおかしいことです。
通勤手当は一見すると非課税のように思われがちですが、実際にはすでに一部が課税対象となっています。
特に社会保険料の計算に含まれることで、知らないうちに「サイレント課税」されているとも言われています。

では、2025年以降に通勤手当がさらに増税される可能性はあるのでしょうか?
2025年以降の増税の可能性

政府は財政健全化を進めるため、さまざまな増税案を検討しています。
その一環として、通勤手当の課税強化が議論される可能性も否定できません。
具体的には、以下のような改正が考えられますよ。
これにより、会社員にとっては実質的な手取りが減る可能性があります。
影響を受ける人と対策

特に影響を受けるのは、長距離通勤者や交通費が高額な都市部で働く人々です。
対策としては、
を採用するなど、従業員の負担を軽減する方法が考えられます。
また
も、通勤手当の削減につながる可能性がありますよ。
通勤手当はすでに社会保険料の計算に組み込まれており、事実上の課税が行われています。
2025年以降、さらなる増税が実施される可能性があるため、企業・個人ともに早めの対策が求められます。
今後の税制改正の動向に注目し、手取りが減少しないような工夫が必要になるでしょう。